フリーランスに向いている人・向いていない人の特徴とメリット・デメリット

「会社員として働き続けることに限界を感じている」「自分がフリーランスに向いているか分からない」
こんな悩みを抱えていませんか?
わたしは現在、自営業として採用コンサルタントやキャリアカウンセラーの仕事をしていますが、もともとは会社員でした。
社内の他の人の分の仕事もして長時間労働になったり、さらには上司からのハラスメントを受けて心身ともにボロボロになっていた時期があります。
そこから独立して、今では自分の強みを活かせる仕事で自由な時間と収入アップの両方を実現しています。
そこで今回は、「フリーランスに向いている人・向いていない人の特徴」「フリーランスとして働くメリット・デメリット」をご紹介します。
フリーランスの職種の種類や成功する実践的なポイントも解説していきますので、今の働き方にモヤモヤを感じているなら、ぜひ最後まで読んでみてください。
フリーランスに向いている人の特徴6選

フリーランスに向いている人の特徴6選を下記に紹介していきます。
- 自己管理ができる人
- 変化を楽しめる人
- 成果主義を好む人
- 自己研鑽ができる人
- 採算意識のある人
- 自走ができる人
(1)自己管理ができる人
フリーランスに向いている人の特徴として「自己管理ができる人」があげられます。
具体的には、自分の行動や時間、体調や感情をコントロールしながら、安定して成果を出す力がある人のことです。
会社員とは違って、フリーランスには決まった出勤時間も上司からの指示もありません。
だから、自分でスケジュールを立てて行動できないと、納期に間に合わなかったり、生活リズムが崩れてパフォーマンスが落ちることがあるんですね。
たとえば、毎朝決まった時間に仕事を始める、タスクを可視化して優先順位を決めてから取り組む習慣は、自己管理には欠かせません。
また、体調やメンタルの管理も重要で、睡眠・食事・運動などの生活習慣を整えることで、継続的に良いパフォーマンスを保つことができます。
自由だからこそ、自分を律する力が求められるのがフリーランスなんですね。
(2)変化を楽しめる人
フリーランスに向いている人の特徴として「変化を楽しめる人」があげられます。
フリーランスは環境や市場ニーズの変化が激しいので、安定よりも柔軟さが求められる働き方だからです。
だからこそ、時代の流れを読んで、必要に応じてターゲット層や提供するサービス内容を変えていくことが大切なんですね。
たとえば、以前は対面でのサービスが主流だった分野も、コロナ禍をきっかけに一気にオンライン化が進みましたよね?
こういった変化に対して拒まずに、逆にチャンスとして乗りこなせる人ほど活躍できます。
変化の波に溺れるのではなく、まるでサーフィンのように波を読んで、勢いを利用して自分の進路を切り拓くことが重要なんですね。
時流をつかみ、柔軟に舵を切れる人は、フリーランスとして長く活躍していく力を持っています。
自ら学んで進化を続けられる人こそ、変化を味方につけていけるんですね。
(3)成果主義を好む人
フリーランスに向いている人の特徴として「成果主義を好む人」があげられます。
フリーランスは、会社員のように毎月固定給をもらう仕組みではなくて、自分の働きや成果に応じて報酬が発生するからです。
なので、「やったぶんだけ稼ぎたい」「努力が報われる働き方がしたい」と考える人には特に相性が良い働き方なんですね。
会社員の場合、たとえ早く仕事を終えても就業時間は拘束されて、追加の業務を手伝うこともあります。
優秀な人ほど業務量が増えるのに、給料は変わらないケースも少なくありません。
一方、フリーランスであれば、業務の効率化やスキルアップによって短時間で仕事を終わらせることができて、その分自由な時間を確保できます。
結果として実質的な時間単価を上げていくこともできるので、
成果主義の環境で自分の力を試したい人には、フリーランスという働き方がぴったりなんですね。
(4)自己研鑽ができる人

フリーランスに向いている人の特徴として「自己研鑽ができる人」があげられます。
フリーランスは、会社員のように社内で研修があったり、誰かが教えてくれることもないため、必要な知識やスキルは自ら能動的に学んで、常にアップデートしていく必要があるんですね。
特に最近は技術進化のスピードが早いので、情報感度が低いとあっという間に時代に取り残されてしまいます。
AIなどのテクノロジーの発展によって、これまで人が担っていた業務が自動化されることも増えていて、影響を受けやすいビジネスではサービス内容の見直しも必要です。
たとえば、単純な事務作業や文章の作成代行など、AIで代替可能な業務をメインにしていた場合、
今後はより高度な提案力や戦略設計など、AIでは補えない価値を提供する方向へシフトしていくことが求められます。
だからこそ、自ら学び、柔軟に変化できる人はフリーランスとして強みを発揮しやすいのです。
(5)採算意識のある人
フリーランスに向いている人の特徴として「採算意識のある人」があげられます。
会社員は毎月固定の給料が支払われますが、フリーランスは自分で収入を生み出す必要があるため、常に収支バランスを意識しながら働くことが求められるからです。
たとえば、サービスを提供してみたものの、想定よりも工数がかかりすぎて利益が出ない、もしくはターゲット層が想定よりも少なくて集客が難しいといったケースもあるんですね。
そういったときには、提供内容や価格、時間配分、ターゲット層を見直して、採算がとれるビジネスモデルへと改善していく柔軟さが必要です。
収支を見ながら優先順位をつけて、利益率を保つことができる人は、長期的に安定してフリーランスとして活動していきやすくなります。
利益を意識した行動をとることは、持続可能な働き方につながる大切なスキルなんですね。
(6)自走ができる人
フリーランスに向いている人の特徴として「自走ができる人」があげられます。
会社員とは違って、フリーランスには上司やマネージャーが存在しないので、業務の指示や進捗管理をしてくれる人はいないからです。
そのため、自分で仮説を立ててリサーチして、課題を見つけて解決していく力が求められるんですね。
たとえば、集客に課題があった場合には、ただ嘆いたり、誰かが教えてくれるのを待つのではなくて、
ターゲットの行動を調べたり、競合の動きを分析して改善策を考える必要があります。
さらに、計画を立てて実行し、振り返って修正していくサイクルを自らまわしていく「推進力」がフリーランスには不可欠なんですね。
「誰に何を言われなくても自ら行動する」という姿勢がある人は、環境の変化に強く、安定した成果を出し続けやすくなります。
自走できる人ほど、コミュニケーションコストがかからないうえに、クライアントや周囲の関係者からも信頼されて継続的な仕事にもつながっていくんですね。
フリーランスに向いていない人の特徴6選

フリーランスに向いていない人の特徴6選を下記に解説していきます。
- 営業力がない人
- 受け身で指示待ちの人
- 他責思考の人
- 自己管理ができない人
- 交渉力がない人
- 安定を好む人
(1)営業力がない人
フリーランスに向いていない人の特徴として「営業力がない人」があげられます。
会社員であれば、上司や営業部門が仕事をとってきてくれる場合もあるかと思いますが、フリーランスは基本的にすべて自己完結なので、自分で集客をしたり、営業をして新規開拓しなければ、仕事そのものが発生しないんですね。
つまり、どれだけスキルや経験があっても、仕事を受注できなければ報酬は1円も得られないです。
だから、自ら営業活動を行って、クライアントを獲得する力がなければ、生活は成り立たないので、貯金を切り崩して、結果的に廃業に追い込まれてしまう人も多いんですね。
営業は、単に売り込むことだけではなくて「どんな人に、どんな価値を届けられるか」を考えて、伝える力でもあります。
なので、自分のサービスを必要とする人にしっかりと届けられる力があるかどうかが、フリーランスとして継続的に仕事をしていく上で非常に重要になるんですね。
(2)受け身で指示待ちの人
フリーランスに向いていない人の特徴として「受け身で指示待ちの人」があげられます。
会社員であれば、上司や先輩が仕事の進め方を教えてくれたり、段取りを組んでくれる場合もありますが、フリーランスだとそういった存在がいないので、自分で考えて調べて仮説を立てて行動する姿勢が必要なんですね。
たとえば、ネットで調べればすぐに分かるようなことをいちいち人に聞いたり、誰かに言われてからようやく動くような人は、
クライアント側から「コミュニケーションコストがかかる」と判断されやすく、継続的な取引にはつながりにくいです。
一方で、クライアントの課題に先回りして提案できるような主体性のある人は、信頼されやすく、長期的な仕事につながりやすいです。
そのため、フリーランスとして成果を出し続けるには、受け身の姿勢ではなく、常に自分から動く姿勢が不可欠なんですね。
(3)他責思考の人

フリーランスに向いていない人の特徴として「他責思考の人」があげられます。
他責思考は、うまくいかなかったときに「環境が悪い」「クライアントが悪い」など、原因をまわりの人や環境の責任にしてしまう思考のことです。
フリーランスは会社員と違って、誰かが責任を取ってくれる立場ではなく、すべての結果が自分に返ってきます。
そのため、トラブルが起きても事前にリスクを見越して予防策や代替案(プランB・プランC)を用意しておくことが必要なんですね。
だから、何か問題が発生したときには、自分の責任として捉えたうえで、原因を分析して次に活かすことができる人は、フリーランスとして長く活躍できます。
一方で、他人や環境ばかりを責めて改善しようとしない人は、成長もできずクライアントやまわりの人から信頼も得られないため、フリーランスには向いていません。
そのため、トラブルが起きたときほど、自分でどう行動するかが問われる働き方なんですね。
(4)自己管理ができない人
フリーランスに向いていない人の特徴として「自己管理ができない人」があげられます。
フリーランスは会社員のように決まった出社時間やルールがないため、働く時間や場所、仕事内容も自分で決める必要があるからです。
そのため、自分自身でスケジュールを組み立てて、納期や数字目標に対して計画的に行動する「セルフマネジメント力」が重要なんですね。
たとえば、納期に間に合わなかったり、生活リズムが乱れて体調を崩すなど、管理が甘いと信用を失い、継続的な仕事の依頼も減ってしまいます。
逆に、自分の働く時間を設計して、業務進捗を管理できる人は、フリーランスの自由さを活かして高い成果を出すことができるんですね。
自己管理が苦手な人は、まずタスク管理ツールやスケジュール帳を使って、日々の行動を見える化することから始めましょう。
(5)交渉力がない人
フリーランスに向いていない人の特徴として「交渉力がない人」があげられます。
会社員であれば、契約交渉や条件調整は上司や営業担当が行ってくれることもあるかと思いますが、フリーランスはすべてを自分で対応する必要があるからです。
具体的には、契約書の内容にこちら側に不利な条項があれば、自ら交渉して修正してもらう、業務量が過剰であれば調整する、報酬が安すぎると感じたら値上げ交渉を行うといった対応が求められます。
なので、交渉が苦手なままだと、低単価・高工数の案件ばかりになって、精神的にも金銭的にも疲弊してしまうことがあるんですね。
だからこそ、フリーランスとして継続的に収入を上げていくためには、「対等な立場」で交渉して、自分の条件を適切に伝えるスキルが不可欠なんです。
最初は難しく感じるかもしれないですが、経験を重ねることで少しずつ交渉力も磨かれていきます。
(6)安定を好む人
フリーランスに向いていない人の特徴として「安定を好む人」があげられます。
会社員であれば、たとえ業績がふるわなくても毎月決まった給料が支払われる仕組みですが、フリーランスはそうはいかず、仕事量や成果、契約条件によって、月々の報酬にばらつきが出ることも珍しくないんですね。
特に、サービス内容の見直しやターゲット層の変更、価格改定などを行うときには、一時的に収入が落ち込むリスクを伴います。
これは中長期的により良いビジネスモデルへと転換するための工程なので、目先の安定を手放す覚悟が求められます。
そのため、常に一定の収入がないと不安になる人や、変化を恐れて現状に固執してしまう人は、なかなかフリーランスとして報酬を伸ばしにくい傾向があります。
フリーランスには、リスクも含めて柔軟に対応し、自らの力で道を切り拓けるマインドが必要なんですね。
フリーランスとして働くメリット6選

フリーランスとして働くメリット6選を紹介していきます。
- 仕事を自由に選択できる
- 青天井の報酬を得られる
- 税金の負担が軽減される
- 人間関係のストレスがなくなる
- 定年制度がない
- 働く場所や時間が自由になる
(1)仕事を自由に選択できる
フリーランスとして働く大きなメリットのひとつは、「仕事を自由に選択できる」ことです。
会社員の場合、配属や業務内容は組織の都合で決まることが多いですが、フリーランスは役割や業務範囲が固定されていないため、自分の得意分野や興味のある領域に絞って仕事を受けることができます。
たとえば、自分のスキルを最大限に活かせるプロジェクトに注力したり、新しい分野にチャレンジして専門性を広げることもできるんですね。
苦手な業務やストレスのかかる内容を無理に続ける必要もなく、自分らしい働き方が実現できます。
こうした環境では、常にモチベーションを高く保ちやすくなるので、結果的に高い成果と報酬にもつながります。
(2)青天井の報酬を得られる
フリーランスとして働く魅力のひとつが「青天井の報酬を得られる」ことです。
会社員の場合、毎月の給料は固定されているので、成果を出してもすぐに収入に反映されることは少ないですが、フリーランスは受注できた案件数や単価に応じて報酬が決まるので、努力や成果次第で報酬は大きく伸ばせるんですね。
たとえば、来月収入を増やしたいと思ったら、高単価の案件を受注したり、仕事量を増やすことで月10万、20万と報酬を上乗せすることもできます。
実力がつけば、さらに高い単価で受注できるようになるので、報酬も比例して増えていきます。
このように、フリーランスは上限がない報酬体系の中で、自分の力で自由に収入を設計できるのが大きなメリットなんですね。
(3)税金の負担が軽減される

フリーランスとして働くメリットのひとつに「税金の負担が軽減される」点があります。
会社員の場合、年末調整で限られた控除しか受けられないですが、フリーランスは自分で確定申告を行うので、仕事にかかった費用を「経費」として計上することができます。
たとえば、自宅の一部を仕事部屋として使っていれば、家賃や電気代を仕事分に按分して経費にできますし、業務に必要な書籍やセミナー代も対象となります。
だから、フリーランスだと、売上から経費を差し引いた「利益」に対して税金がかかるため、実質的に支払う税金を抑えることができるんですね。
税金の仕組みを理解して正しく活用することがフリーランスの資産を守るカギとなります。
(4)人間関係のストレスがなくなる
フリーランスとして働くメリットのひとつに「人間関係のストレスがなくなる」ことがあげられます。
会社員の場合、自分で上司や同僚を選ぶことはできず、配属先やチーム編成によっては合わない人と一緒に働くことになりますが、フリーランスは取引先や顧客を自分で選べるので、人間関係の主導権を握ることができます。
たとえば、価値観が合わないクライアントがいた場合は、丁寧に話し合ったうえで折り合いがつかなければ、きりの良いタイミングで取引を終了して、別のクライアントを探すことが可能です。
そのため、自分の裁量で関係性を築けるので、精神的な負担が少なく、心地よい環境で働くことができるのがフリーランスの魅力です。
(5)定年制度がない
フリーランスとして働く最大のメリットのひとつに「定年制度がない」ことがあげられます。
会社員の場合、60歳や65歳で定年退職を迎えて、その後は年金や貯金での生活になりますが、フリーランスには定年制度がないので、何歳になっても自分のペースで仕事を続けることができるんですね。
実際、定年後の生活費に不安を抱える人は多いですが、フリーランスであれば「引退後の生活資金が足りない」と悩むことなく、経験や専門性を活かして仕事を継続できます。
そのため、自分で働き方をコントロールできるため、年齢に縛られず、自由なキャリア設計が可能です。
フリーランスは、年齢に左右されずに働き続けたい人にとっても、魅力的な働き方なんですね。
(6)働く場所や時間が自由になる

フリーランスとして働く大きなメリットのひとつが「働く場所や時間を自由に選べる」ことです。
会社員のように決まった就業場所や勤務時間に縛られることがなく、自分の生活リズムや集中できる時間帯に合わせて働くことができるからです。
特に、毎日の通勤による満員電車のストレスや移動にかかる時間と体力の消耗に悩む人にとっては、フリーランスはストレスから一気に解放される働き方になります。
また、日本企業に多い仕切りのないオフィスでは、電話や雑談が絶えず集中力を保つのが難しい面もありますが、
フリーランスであれば、自宅や静かなカフェなど、自分にとって最も集中できる環境を選ぶことができるんですね。
このように、フリーランスの自由度の高さは、仕事の生産性を高める効果があります。
フリーランスとして働くデメリット4選

フリーランスとして働くデメリット4選を紹介していきます。
- 最初は収入が安定しにくい
- 確定申告の必要がある
- 保険など社会保障が手薄になる
- 全ての意思決定が自己責任となる
(1)最初は収入が安定しにくい
フリーランスとして働き始めたばかりの頃は、収入が安定しにくいというデメリットがあります。
会社員と違って、毎月決まった給料が自動的に振り込まれる仕組みではなく、自分で仕事を獲得しない限り、収入が1円も発生しないからです。
特に開業初期は、どのターゲット層に、どのようなサービスを、いくらで提供するのかといったビジネスの方向性を試行錯誤するフェーズが続くんですね。
その間は収入が上下しやすく、生活が不安定に感じることもあります。
そんななかでも、継続的に新規開拓を行いながら改善を重ねていくことで、徐々に信頼が蓄積され、安定的な案件や継続契約に繋がるようになるんですね。
そのため、初期段階では生活費を数ヶ月分確保しておくなど、計画的な準備が大切です。
(2)確定申告の必要がある
フリーランスとして働く場合、会社員のように年末調整を会社でしてもらえるわけではなく、自分で確定申告を行う必要があります。
具体的には、1年間の売上から経費を差し引いて利益を算出して、その利益に対して所得税や住民税などを計算し、税務署に申告します。
そのため、最低限の税務知識は持っておいたほうがいいです。
最近では、会計ソフトを使えば、クレジットカードや銀行口座を仕事用とプライベート用に分けて連携するだけで、自動で帳簿づけができるので、申告書の作成もスムーズにできます。
できたら、日々の取引をこまめに記録することが、確定申告の手間を大きく減らすポイントになります。
(3)保険など社会保障が手薄になる

フリーランスとして働く場合、会社員と比べて社会保障が手薄になる点は大きなデメリットのひとつです。
会社員であれば、健康保険や厚生年金は会社と折半で支払われますが、フリーランスは「国民健康保険」「国民年金」などを自分で全額負担しなければなりません。
また、会社員であれば体調を崩して働けない場合に「傷病手当金」などが支給される制度がありますが、フリーランスには基本的にそのような保障はありません。
そのため、働けなくなったときのために生活防衛資金を数か月分蓄えておくことが重要です。
万が一に備えて、民間の保険を活用するなどの対策も必要になります。
こうしたリスクに備えたうえで、収入を伸ばしていくことが、フリーランスとして長く続けるための鍵となります。
(4)全ての意思決定が自己責任となる
フリーランスとして働く場合、すべての意思決定が自己責任となる点は大きな特徴であり、同時にデメリットでもあります。
会社員であれば、経営方針や業務内容は上司や経営陣が決定して、その判断に従って動くので、責任の所在も分散されますが、フリーランスは契約内容、価格設定、取引相手の選定まで、自分で判断する必要があります。
その結果、トラブルが発生しても誰も責任をとってくれません。
だからこそ、自発的な情報収集力と冷静な判断力が求められるんですね。
最終的に自分で決めて、自分で結果を受け止める力が必要です。
リスクを最小限に抑えるためにも、契約書の確認や業務内容の明確化など、日頃からのリスクマネジメントが欠かせません。
フリーランスの職種の種類5選

フリーランスの職種の種類5選を紹介していきます。
- ITエンジニア
- ライター系
- ディレクター・コンサルタント
- マーケティング系
- クリエイター系
(1)ITエンジニア
フリーランスの職種の中でも需要が高いのが「ITエンジニア」です。
ITエンジニアは、Webサイトやアプリの開発、システム設計、インフラ構築など、IT関連の技術を使ってサービスをつくる専門職です。
プログラミングスキルが求められますが、リモートワークとの相性が良いので、実力次第で高単価の案件も受注できます。
実務経験やポートフォリオ(過去の制作実績)を提示できると、受注率が高まります。
特に、フロントエンド(画面側)やバックエンド(システム側)、インフラなど、専門分野に強みがあると差別化もしやすく、安定した収入にもつながります。
(2)ライター系
フリーランスの職種として需要が高まっているのが「ライター系」の仕事です。
Web記事の執筆やSEOライティングに加えて、セールスライターや動画シナリオライターなど、多様な分野に広がりがあります。
セールスライターは、商品の魅力を引き出して、購買意欲を高める文章を作成する職種で、マーケティング知識が求められます。
動画シナリオライターは、YouTubeや企業PR動画などの構成やセリフを考える仕事です。
いずれも読者や視聴者の心を動かす力が必要とされるため、リサーチ力や構成力、コピーライティングのスキルを磨くことで高単価案件につながる可能性があります。
このように、ライターの仕事は、未経験からでも始められるものもあり、実績次第で着実にステップアップできる職種です。
(3)ディレクター・コンサルタント

フリーランスの職種のなかでも、ディレクターやコンサルタントは「上流工程」を担う専門職です。
ディレクターは、Web制作や動画編集、マーケティング施策などのプロジェクトにおいて、進行管理や品質管理、関係者との調整を担当します。
一方、コンサルタントは、課題解決や戦略設計などのアドバイスをして、クライアントの意思決定を支援する役割を担います。
いずれも高単価な案件が多い反面、課題発見をするための経験や実績、論理的思考力が必要とされます。
チーム全体の動きを見渡す視野や、相手の意図をくみとるコミュニケーション力が求められるため、これまでの経験を活かしやすい職種です。
そのため実務だけでなく、全体をまとめるリーダーシップがある方に向いています。
(4)マーケティング系
マーケティング系のフリーランスは、商品やサービスの魅力を伝えて「売れる仕組み」をつくる役割を担います。
職種にはWeb広告運用、SNS運用代行、SEO対策、メルマガ設計、セールスコピー制作、データ分析などがあります。
クライアントの事業課題をヒアリングして、売上につながる導線設計や改善提案を行うため、論理的思考力と実行力が求められます。
なかでも、顧客心理をつかむ力や数字を読み取るスキルがあると重宝されます。
企業のマーケティング部門に外部パートナーとして関わるケースも多いので、単価も高めの傾向にあります。
そのため、マーケティング系は企画から運用まで幅広く携われるので、ビジネス視点を鍛えたい人にもおすすめの分野です。
(5)クリエイター系

クリエイター系のフリーランスには、Webデザイナーやグラフィックデザイナー、動画編集者、イラストレーター、写真・映像クリエイターなどがあります。
クライアントの意図を汲み取り、視覚的に魅力を伝えるアウトプットが求められるため、デザインスキルやツールの操作技術はもちろん、ヒアリング力や提案力も必要です。
たとえば、PhotoshopやIllustrator、Premiere Proなどのソフトが使えると仕事の幅が広がります。
SNSの発達により、動画や画像コンテンツのニーズが高まっており、クリエイター系は今後さらに需要が見込まれる職種です。
そのため、クリエイター系はセンスと技術を活かしながら自由に働きたい人に向いています。
フリーランスとして成功する4つのコツ

フリーランスとして成功する4つのコツを下記に紹介していきます。
- 継続的に自己研鑽する
- 市場選定とブランディングを徹底する
- クライアントとの信頼関係を構築する
- 集客・新規開拓の仕組みづくりをする
(1)継続的に自己研鑽する
フリーランスとして成功するためには、自分のスキルや知識を高めるために、自発的に学び続ける継続的な自己研鑽が欠かせません。
会社員と違って研修制度や上司の指導がない分、自ら情報収集を行い、時代に合ったスキルを身につけていく必要があります。
特に最近では、AIが発達したりと、技術やトレンドの変化が早いため、数年前の知識が通用しないこともあります。
たとえば、マーケティングであればSNS広告やSEOの最新手法を学んだり、デザイナーであれば新しいツールやUI/UXのトレンドを把握するなど、アップデートは必須です。
学んだことをすぐに仕事で実践することで、成果にもつながりやすくなります。
(2)市場選定とブランディングを徹底する
フリーランスとして成功するためには、「市場選定」と「ブランディング」の戦略が欠かせません。
市場選定は、どの分野・業界・ターゲット層を相手にサービスを提供するかを決めることです。
たとえば、ライターでも美容業界に特化するのか、BtoB向けにするのかで、必要な知識や報酬単価が大きく異なるんですね。
また、ブランディングは、自分の強みや専門性を明確にし、顧客から選ばれる存在になるための戦略です。
プロフィールや実績の見せ方、SNSやポートフォリオの発信内容まで一貫性を持たせることで、他のフリーランスとの差別化ができます。
市場で求められることと自分の強みが重なるポジションを見極めることが、継続的な受注と高単価案件につながります。
(3)クライアントとの信頼関係を構築する

フリーランスとして長期的に活躍するためには、クライアントとの信頼関係を築くことがとても重要です。
信頼関係とは、単に納期を守るだけでなく、報告・連絡・相談(いわゆる「ホウレンソウ」)を丁寧に行うことや、約束した品質を継続的に提供することから生まれます。
また、相手の意図を汲み取り、先回りして提案できるようになると「この人に任せたい」と思われて、継続的な受注につながりやすくなります。
ちょっとした納期の相談やトラブル対応でも、誠実に対応する姿勢が評価され、結果的に継続案件や紹介に繋がるケースも多いんですね。
そのため、フリーランスは成果だけでなく、人としての信頼が報酬やチャンスを引き寄せる鍵になります。
(4)集客・新規開拓の仕組みづくりをする
フリーランスとして安定的に仕事を得るには、集客や新規開拓の「仕組みづくり」が重要です。
だから、単発商品の営業活動をするだけではなく、自動的に見込み客と接点を持てる導線を作ることが鍵になります。
たとえば、ブログやSNSで自分の専門性を発信したり、ポートフォリオサイトを作って実績を見せることで、仕事の依頼が来やすくなります。
また、オンライン上でスキルを販売できるクラウドソーシングを活用するのも有効です。
新規開拓の仕組みを整えておけば、営業に時間をかけすぎることなく、業務に集中できる環境を作れるため、継続的に顧客と出会う仕組みが、フリーランスの安定収入に直結します。
フリーランスとしてのわたしの経験談

わたしも元々は会社員として働いていましたが、上司からのハラスメントや、他の人の業務を巻き取る日々が続いていて、長時間労働でも給料はほとんど変わりませんでした。
心身ともに限界を感じるようになって「このままでは壊れてしまう」と思ったのが独立を考え始めたきっかけです。
通勤の満員電車も大きなストレスで、身支度と通勤時間を合わせると、月に40時間ほどが失われていました。
フリーランスになってからは、そうした無駄な通勤や社内会議、関係ない業務から解放されて、自由に使える時間が増えただけでなく、ストレスも大きく軽減されました。
今では自営業の採用コンサルタント、マーケター、キャリアカウンセラーとして、自分の強みを活かしながら会社員時代以上の収入を得ています。
自分の裁量で働ける今の生活は、仕事も人間関係も自由に選択できて幸せな毎日を送っています。
ちなみに、「人生を好転する習慣方法」についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ

今回は、フリーランスの向き不向きやメリットデメリット、フリーランスとして成功するコツについて解説しました。
フリーランスとして働きたい人は、継続的に自己研鑽をして、市場選定・ブランディングを徹底し、クライアントと信頼関係を継続することが成功させるコツとなります。
さらに、継続的に仕事をし続けるには、集客・新規開拓の仕組みを確立して再現性のあるものにしていくことが重要です。
フリーランスを実現させるには、自分の強みを明確化して、目標設定することがポイントとなります。
また、独立する前に、まずは副業から始めてみることで市場のニーズや自分の適性もわかるのでリスクを軽減させながら実現へと近づけていけます。
わたしは、キャリアカウンセラーやWEBマーケコンサル、ビジネスコンサルタントとしてこれまで多くの女性のキャリア相談を受けてきました。
自己分析のカウンセリングはもちろん、女性の強み発掘や独立支援もしています。
わたし自身、独立して在宅起業したことで、時間や場所に縛られず、人間関係を自由に選択できて快適な毎日を過ごせるようになりました。
今の仕事を続けるかお悩みの方、独立起業、副業などに興味のある方は、ぜひご相談ください。
また、少しでも気になった方は、「3ヶ月で雇われずに自由と収入が叶う動画講座」(LINE友だち追加するだけ無料)をご視聴ください。
さらに、「強みが発掘できる自己分析シート」「副業適性診断シート」「起業・独立適性診断シート」「内向型・外向型・両向型診断シート」「在宅ワーク適性診断シート」「夢を実現する!目標設定シート」もプレゼントしていますので、こちらからお受け取りください。


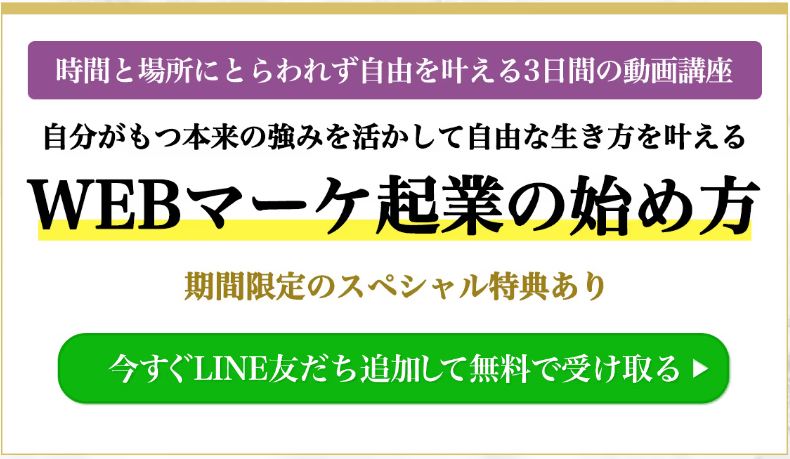
コメント